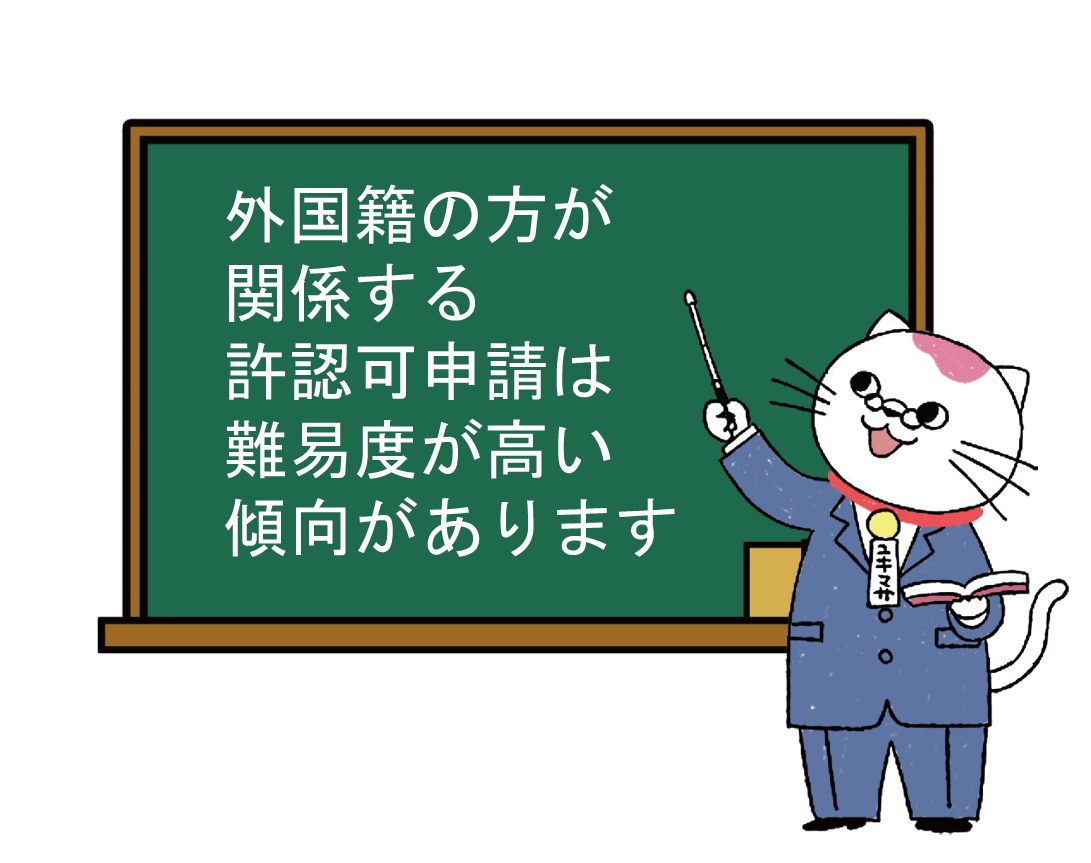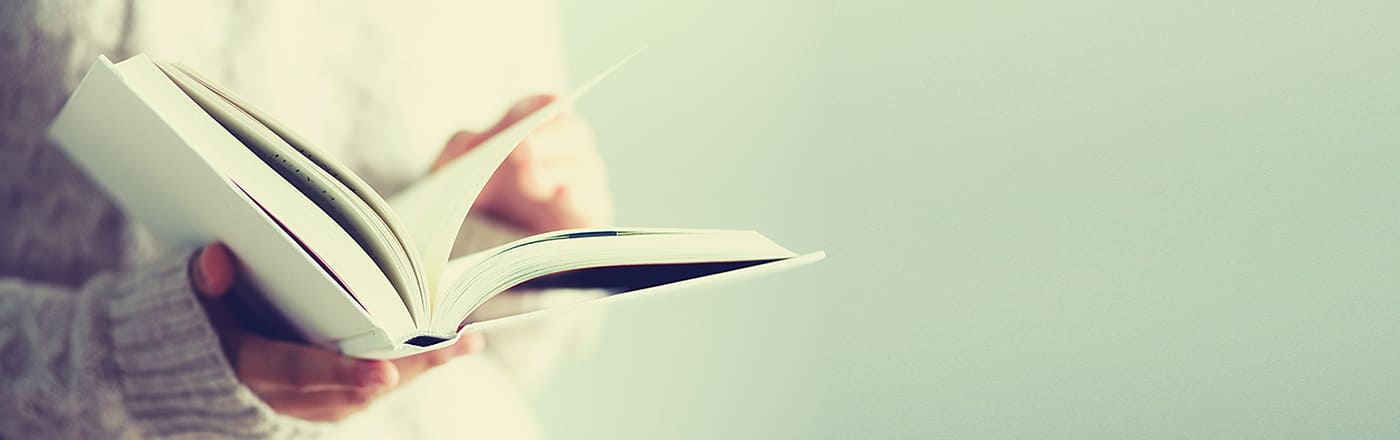
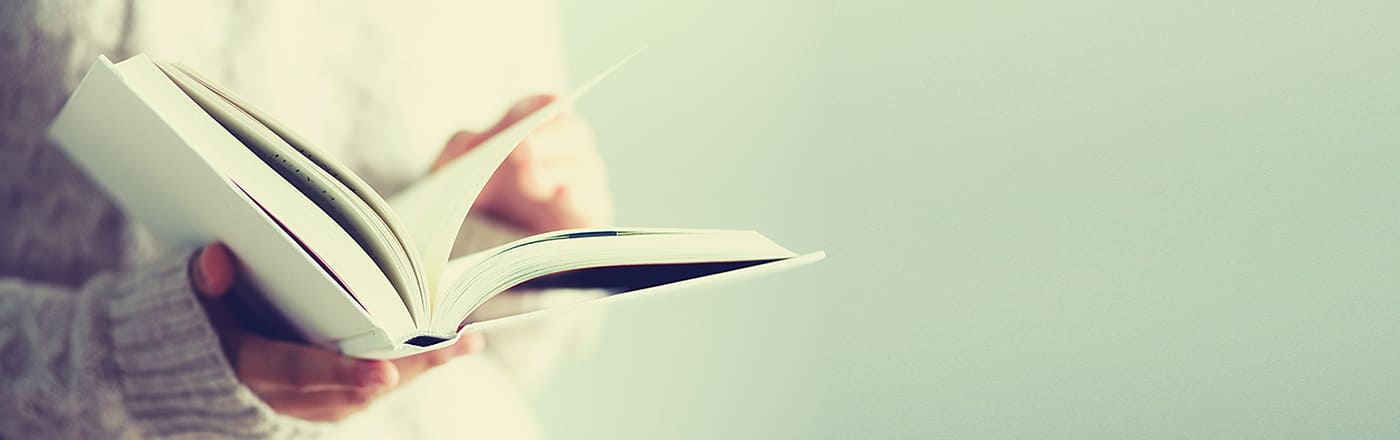
建設業許可とは
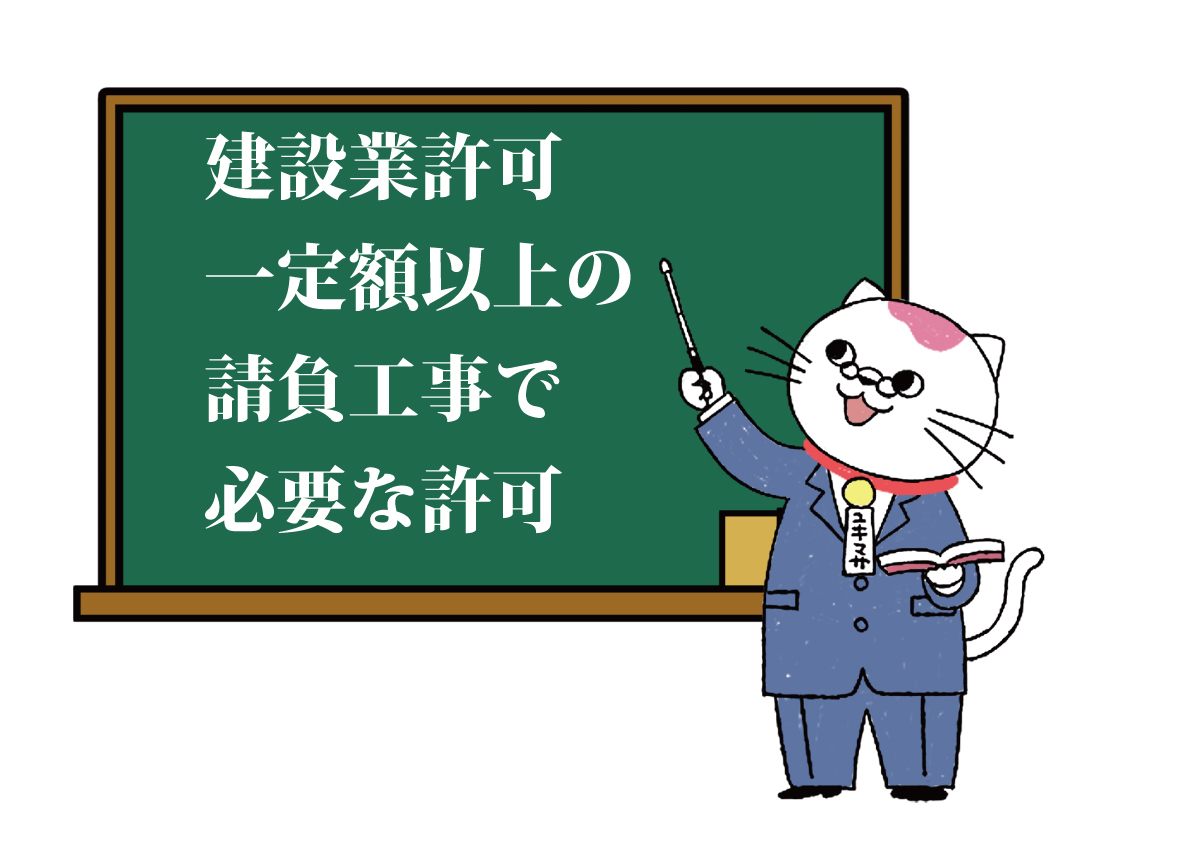
この記事は建設業許可についてご紹介します。
建設業許可とは、一定額以上の建設工事の請負仕事をするときに必要な許認可です。
一定額以上とは、以下の金額になります。
- 500万円以上の工事
- 建築一式工事は1500万円未満
建築一式工事とは、家屋などを建てる工事と思っていただければ。
元請工事で建築確認が必要な工事ですね。
工事の種類は元請・下請を問いません。
現在は法令順守の意識の高まりで、500万円以下の工事でも許可が無いと現場に入れない事が多くなっています。

許可が無いと仕事を回せないと言われて行政書士やまだ事務所に相談に来る人は多いニャ~
また建設工事の定義も建設業法で決められています。
基本的には工事の完成を請負う請負契約が建設工事と定義されています。
例えば庭木の剪定や建物の保守点検は建設工事に該当しません。
また工事現場に作業員を応援に出す人工出しや常用工事も建設工事ではありません。
建設工事の種類が重要になるのは、建設業許可や公共工事の入札です。
許可を取得する際に、建設会社の経営や実務経験の立証が必要です。
証明には工事の注文書などを提出することで行います。
常用工事や保守点検は建設工事ではないので、証明材料にならないことです。
また公共工事の入札の際に、経営事項審査(経審)と呼ばれる手続きを行います。
この時に重要なのが完成工事高(売上)で、上記の作業は完工高に含むことができません。
(その分の売り上げが減るのでP点が低くなります。)
建設業許可の種類
次に建設業許可の種類について。
建設業許可は以下の4つの属性があります。
- 都道府県知事許可
- 国土交通大臣許可
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
さらに細かく分けると以下のようになります。
- 都道府県知事×一般建設業許可
- 都道府県知事×特定建設業許可
- 国土交通大臣×一般建設業許可
- 国土交通大臣×特定建設業許可
まずは都道府県知事許可から。
こちらは1つの都道府県のみ営業所がある場合に取得します。
次に国土交通大臣許可ですが、こちらは複数の都道府県に営業所を設置する際に必要な許可。
例えば大阪府と兵庫県に営業所を置くという感じですね。
特定建設業許可から、これは4500万円以上の下請け工事を出す場合に必要な許可です。
(建築一式工事の場合は7000万円)
特定建設業は大規模な工事を受注する企業に必要な許可です。
一般建設業許可よりも財務内容や専任技術者、監理技術者など要件が厳しくなっています。
これは下請け業者の保護の為に必要な措置です。
一般建設業許可はそれ以外の工事を受注するために必要な許可です。
下請け工事に4500万円出さない場合は、受注金額に制限はありません。
建設業許可は工事の種類ごとに29種類の許可業種が存在します。
許可の効力は取得した許可業種のみに適用されます。
例えば大工工事業で取得した場合、大工工事のみ500万円以上の工事が可能です。
左官工事や塗装工事は大工の許可では500万円未満までです。
建設業許可の申請方法
次に建設業許可の申請方法です。
許可申請を管轄する役所に申請書一式を提出することで行います。
都道府県知事の場合は、都道府県庁の建設業課など。
国土交通大臣許可は地方整備局。
申請書は建設業法上で決まった様式と各種添付書類があります。
添付書類の例としては、納税証明書や登記されていないことの証明書、確定申告書、工事契約書や注文書、卒業証明書や資格証などがあります。
少し前までは紙の書類で提出していました。
令和5年1月より電子申請(JCIP)で行う役所が大半になりました。
(大阪府、京都府、兵庫県など近畿圏の役所は実施期間未定)
いまのところ電子申請以外に紙の申請書も受け付けております。
(令和5年4月現在)
標準処理期間は、大阪府の場合30日で地方整備局は90日です。
意外と時間が掛かりますので、余裕をもったスケジュール調整が必須。
建設業許可の審査基準
建設業許可は6つの要件が存在します。
役所では申請者が要件を備えているかを書面で確認します。
(面接試験とかはありません。)
一般建設業許可の要件は以下の通りです。
- 常勤役員等がいること
- 営業所ごとに専任技術者がいる
- 欠格要件・誠実性要件に該当しない
- 要件を満たした営業所がある
- 500万円以上の財産的基礎
- 社会保険に加入している
建設業許可には上記の要件があります。
この中で特に難しいのは、常勤役員等と専任技術者です。
建設業許可は人の要件のハードルが高くなっています。

常勤役員等は経営経験が必要不可欠。
この要件が満たせずに経験期間が溜まるのを待つ人は多いニャ
営業所や社会保険は、満たすことが難しくないです。
(お金がかかるけども)
個別具体的な要件は別途にご紹介します。
建設業許可の更新手続き
建設業許可は一度取ったら終わりではありません。
5年おきに更新が必要な許認可です。
手続きは期限の3か月前から受付スタートで、期限の1か月前までに行う必要があります。
(ギリギリでも受け付けてくれるけど、許可証が届くのが遅くなる)
更新申請する際には、いくつかの条件を満たしている必要があります。
- 変更事項が無い
- ある場合は変更届を提出済み
- 5年分の決算変更届
変更届ですが、建設業許可は一定の変更が生じたときは届出が必要です。
例えば役員や営業所、常勤役員等や専任技術者など。
これらは提出期限があります。
特に常勤役員等と専任技術者は1日でも欠けたら許可取り消しになります。
時折、変更届が提出されていないことも。
この場合は変更申請の前に変更届を出して、登録状況を最新のものにする必要があります。
つぎに決算変更届です。
確定申告終了後、4か月以内に役所に決算報告を行います。
決算変更届の提出でその間の営業がなされていたことを証明します。
更新申請をするためには、5年分の決算変更届が必要です。
更新書類の提出時に、5冊分の決算変更届の持参が必要。
決算変更届が抜けていると、更新が出来なくなります。
この場合は大急ぎで抜けている分の決変の書類一式を作ることになります。
(提出時に担当官から指導が入ります)
更新手続きですが、それなりにボリュームがあります。
ペラ1枚で済まないので、意外と時間がかかります。
建設業許可の失効理由と再取得方法
建設業許可の失効と再取得方法について。
建設業許可は意外と簡単に失効してしまいます。
- 更新を飛ばした
- 常勤役員等や専任技術者が欠けた
- 役員が欠格事由に該当した
特に建設業許可の失効で多いのが上記3つになります。
更新を飛ばしたは、単純に5年に1回の更新申請を行わなかった。
もしくは期限までに間に合わなかったケースです。
(変更届や決算変更届の未提出で作業が追いつかなかった)
常勤役員等や専任技術者が欠けたことです。
突然の退職や退任(役員)、突発的な事故や病気等…
人間である限りは、突発的なトラブルが発生します。
これの怖いところは1日でも居なければ、許可の取消になります。
ちなみに黙っていて後に発覚した時は、5年間は許可の取り直しができなくなります。
役員や令3条使用人(支店長・営業所長)の欠格事由について。
何らかの事情で警察のお世話になったときです。
懲役刑や禁錮刑に該当する様な刑罰を受けた場合など。
次に許可の再取得方法について。
許可の要件を満たした後に新規申請することになります。
当然ながら許可番号は変わります。
難易度ですが、更新を飛ばした場合は比較的に難しくないです。
(要件自体は見たいしていることが多いため)
ただ欠格要件や専技、常勤役員等の場合は難易度が高い傾向があります。
建設業許可については、以上となります。
かなりザックリとした文書になりましたが、要点は全部かけたと思います。